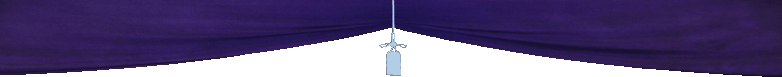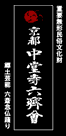【一山打ち(いっさんうち)】
念仏曲、発願から結願まで全曲を演じること。盂蘭盆を中心に奉納公演、地元公演で行う事が多く、講中の重要な舞台である。
【豆太鼓】
六斎特有の太鼓。直径十五センチ程度の平に子牛の腹の皮を限度いっぱいに張っており、鼓のような鋭い音がする。空也上人が、大衆布教の時に瓢箪を叩いたことに由来する。
【側(か)】
豆太鼓の胴部分を言う。転じて六斎の古い形で、豆太鼓の曲を総称する。

豆太鼓
【鉦(かね)】
念仏に使用する鉦と同種であるが、音色、響きともより澄んでいるのが特徴である。六斎では全曲に使用し主として伴奏部を受け持つ。「鉢たたき念仏」と言われたごとくお鉢を叩いたことに由来する。
【すり】
鉦を叩くことを「スル」と言い、使用するバチのことを言う。鉦をスル頭は、鹿の角を輪切りにしたもので、柄の部分は抹香鯨のひげを用いている。近年自然保護の関係で代替品を使用している。

鉦とすり
二丁吊り(にちょうづり)
横並びに二丁吊られた鉦の事。当会では祇園ばやし以外全曲に使用する。

二丁吊り
一丁吊り
祇園ばやしでのみ使用する。当会では黒の漆塗りで京錺を施した枠に六枚の鉦を吊る。その外に、提灯や飾り房、金銀焼香太鼓をセットし、開始から最終まで一山打ちの舞台背景となる。

焼香太鼓
【ぶち(打棒)】
六斎では、バチのことを言う。堅ぶちは豆太鼓用。丸ぶちは普通の太鼓用。太ぶちは大太鼓用。踊り方や曲目により太鼓の大きさと種類が違いぶち(打棒)も機能的に変わる。
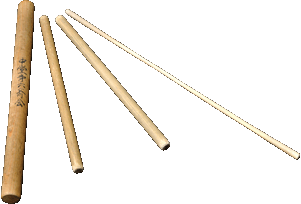
ぶち
【上(かみ)打ち】
太鼓曲においてリードパートを受け持つソロの打ち手。当会においては、導入部の曲は熟練者が、その他の曲は若手、中堅者が打つ。
【しずみ】
六斎における唯一の旋律楽器は笛である。そのユニゾン部分で、落ち着いた中低音をゆったりとした奏法で発する長音の事。
【狂言】
古典芸能の能・狂言とは違い、宗教的な教えを説く大念仏狂言の事である。洛中には、円覚上人が創始した壬生寺や嵯峨の清涼寺、定覚上人が創始した千本ゑんま堂の狂言があり、京の三大念仏狂言といわれている。因みに、当会では歴史的な事情から、橋弁慶・棒振り・土蜘蛛を壬生狂言から取り入れている。
【相打ち】
豆太鼓で行うことが多い。「表」は曲をリードし、「裏」は間合いのリズムを拾っていく。双方の息のあった掛け合いが見所で太鼓芸の一つである。当会では、「すがらき」「さらし」「七草」が相当する。
【据え打ち】
本来六斎は太鼓を持って踊りながら打つ太鼓踊りであるが、四つ太鼓だけが固定した太鼓台に四つの太鼓を据えて打つ。太鼓曲であると同時に個人芸的要素も兼ね備えている。当会では、二本ぶちの途中「六つ太鼓」にも転じる。
【デレデレ太鼓】
四つ太鼓の高度な打ち方。利き手とそうでない手との強弱が無く、より細かいぶち捌きでテンポよく打ち、玄人受けする太鼓芸の一つ。
【地廻り】
太鼓曲の中で、その場で振りをする太鼓踊りに対して、躍動し移動しながら踊る太鼓芸のことを言う。祇園ばやしの「流し」部分や、獅子太鼓がそれに当たる。転じて、獅子の舞いを言う事もある。
【乱れ打ち】
表と裏の絡みのなかで、双方が調和し、流れるような太鼓のリズムで打ち手が移動しながら徐々にテンポアップを図る打ち方。
【反し打ち】
相打ちの一種であるが、特に歓喜勇躍する獅子の勝利を祝す「攻め太鼓」の部分を言う。
【獅子】
太平と正義の象徴。頭(かしら)、尾(お)、二人ペアーで演じる。日本各地に見られる「獅子舞い」は、胸部から腹部が露出しているが、六斎の獅子は胴が袋状になっていて脚以外の身体が全て隠れているのが特徴。「腰立ち」「肩立ち」「しょんべん遣り」「どんぴしゃ」「二丁返り」「股ぬき」「蚤取り」「碁盤乗り」などの技がある。体力と技術が必要で文字通り六斎の花形芸である。しかし、近年教育や社会環境の変遷に伴い、継承、養成に苦労している。

獅子の頭
【蜘蛛の巣(糸)】
土蜘蛛が、獅子との絡みで投げかける糸。素材は極薄の半紙で長さ約三メートルを鉛の芯に巻きつけ、幅一ミリ程度に切り刻んだもの。各講中では、独自の製法がある。獅子に掛かった蜘蛛の巣を一部持ち帰り、神棚に供えると厄除けに、また芯を財布に入れておくと金運に恵まれる、との言い伝えがある。