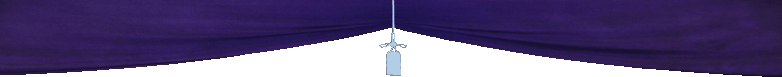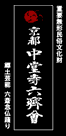六斎念仏踊りとは
今から約千百年前、京洛の街々に疫病が蔓延し多数の死者が出た。当時仏教の末法思想の影響で人々が不安に陥ったその時、第六十代醍醐天皇の皇子といわれる市井の聖、空也上人が托鉢用の鉢と瓢箪を打ち鳴らし洛中の街角で「南無阿弥陀仏」を唱え人々の不安を取り除いた。この鉢叩き念仏が六斎念仏踊りの起源とされている。

洛中をゆく六斎の獅子舞(拾遺都名所図会)
仏教で言う六斎日とは、毎月八日・十四日・十五日・二十三日・二十九日・三十日の六日を言い、この日は悪鬼などが勢いを得て、人々に災いを及ぼすとされている。この日に、鉦と太鼓を打って念仏を唱えることから、「六斎」の名が生まれた。そして、精霊供養の盂蘭盆会と相まって発展し、今日の原型が造られたのであろう。
近世に入ると、周辺の農村地域で都会の消費生活に憧れる若者の流失を防ぐため、多くの六斎講中が形成された。そして、洛中でそれぞれの技を競い合ううち、広く民衆の支持を得る為には芸能化への道が避けて通れないものとなりいくつもの派に分かれて行った。
「中堂寺六斎念仏踊り」は、宗教的色彩が薄れ、芸能性・大衆性を多分に取り入れたものである。折りしも文化の中心が江戸から上方に移り始めたことにも影響され、長唄・地唄・太鼓の曲打ち・獅子舞い等が導入されたことは、六斎の大衆芸能化に拍車をかけたものと思われる。現在の各六斎講中の採っている形式は、およそこの頃に確立されたものである。
大正・昭和にかけて、その隆盛を誇ったものの、戦争での中断・後継者難等で数団体の活動に止まっていた。しかし、昭和五十八年に文化庁から重要無形民俗文化財に指定されたことを受け、現在は十数団体による六斎連合会が組織され、お盆を中心に幅広く活動している。